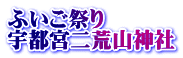●新渡戸稲造先生は、いかに刀を重視していたかを語り、「象徴としての刀」の存在を説明している。
刀は武士の魂十五歳にして成年に達し、行動の自由を許さるる時に至れば、いかなる業にも用うるに足る鋭利なる刀の所有を誇りうる。この兇器の所有そのものが、彼に自尊ならびに責任の感情と態度を賦与する。「刀は伊達にささぬ」。彼が帯におぶるものは心におぶるものーー忠義と名誉の象徴である。大小二本の刀ーー太刀小刀、もしくは刀脇差と呼ばるーーは決して彼の身辺を離れず、家にありては書斎客間のもっとも目につきやすき場所を飾り、夜は容易に手の届く所に置かれて彼の枕頭を守る。刀は不断の伴侶として愛せられ、固有の呼び名を付けて愛称せられ、尊敬のあまりほとんど崇拝せられるに至る。史学の祖(註‥ヘロドトス、~紀元前四二〇年以前)はスキユタイ人が鉄のえん月刀に犠牲(いけにえ)を捧げたことを一の奇聞として録しているが、日本では多くの神社ならびに多くの家庭において、刀をば礼拝の対象として蔵している。もっともありふれた短刀に対しても、適当の尊敬を払うを要した。刀に対する侮辱は持ち主に対する侮辱と同視せられた。床に置ける刀を不注意に跨ぎし者は禍(わざわい)なるかな!》
象徴としてでなく武器として使用する時の心構えについては、武士道は刀の無分別なる使用を是認するか。答えて日く、断じてしからず! 武士道は刀の正当なる使用を大いに重んじたるごとく、その濫用を非としかつ憎んだ。場合を心得ずして刀を揮(ふる)った者は、卑怯者でありホラフキであった。重厚なる人は剣を用うべき正しき時を知り、しかしてかかる時はただ稀にのみ来る》
●良く聞かれることに、銃砲刀剣類に関する法律で刀所持するに特別な許可が必要なんでしょ!!と聞かれます、、。日本刀はとても簡単な手続きで所持ができるのです。
★日本刀を所持するには
○我が国では、公衆の安全を確保するため、銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)で鉄砲、刀剣の所持や取り扱いを厳しく規制しています。公共の場での使用・所持の許可制度、刀剣類 の製作承認制度、美術品としての刀剣類の登録制度等を設けるとともに、刃渡6cmを超える刃物 の携帯を禁止するなどの規制を設けています、しかし、日本刀は、我が国が世界に誇る文化遺産で、所定の登録がしてあれば、この登録制度によって、美術品としての日本刀は、誰でも購入でき所持できるという道が開かれています。たとえば道場の稽古にいくにおいて刀を持って電車にのって行ってもなんの問題もありません(但し登録証と稽古着の所持は必要)。
○刀剣類には、たち、刀(刃渡60cm以上)、わきざし(刃渡30cm以上)、短刀(刃渡30cm未満) 、剣、やり及びなぎなたがあります。
○登録証の付いていない刀剣類は、譲り受け、譲り渡し(売り、買い、もらうことなど)はできません。もし登録証のない刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署へ「すみやかに」刀剣 類を発見した旨を連絡し、指示にしたがい警察署へ持参します。警察署は、刀剣類の発見を受理し、「発見届出清書」を交付し、各都道府県の教育委員会で実施している登録審査会の日時と場所を教えでくれます。
○登録審査は、その刀剣類が美術品としてまたは骨董品として登録できる条件を備えているかど うかを鑑定するものです。刀の形をしていても、古来の日本刀の製法で作られていなければ登録はできません。
○登録証の付いている刀剣=美術品と認定された刀剣類は、誰でも所持することができます。
○刀剣類を譲り受けた時は、届け出なければなりません。登録証を発行した都道府県の教育委員会あてに新しい所有者が、所有者変更届出書(県のHPで入手出来ます)を却日以内に提出します。「所有者変更届出書」をコピーして必要事項を記入し(印鑑不要)、送付するだけと手続きは簡単です。譲り渡した場合は、相手に届出をしてもらいましょう。
○所有者変更の届けをしていない場合は、銃刀法に違反している状態であり、登録証を紛失した時の再交付手続きも面倒になります。 例えば、下記のような場合に所有者変更届出善が必要です。
○我が国では、公衆の安全を確保するため、銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)で鉄砲、刀剣の所持や取り扱いを厳しく規制しています。公共の場での使用・所持の許可制度、刀剣類 の製作承認制度、美術品としての刀剣類の登録制度等を設けるとともに、刃渡6cmを超える刃物 の携帯を禁止するなどの規制を設けています、しかし、日本刀は、我が国が世界に誇る文化遺産で、所定の登録がしてあれば、この登録制度によって、美術品としての日本刀は、誰でも購入でき所持できるという道が開かれています。たとえば道場の稽古にいくにおいて刀を持って電車にのって行ってもなんの問題もありません(但し登録証と稽古着の所持は必要)。
○刀剣類には、たち、刀(刃渡60cm以上)、わきざし(刃渡30cm以上)、短刀(刃渡30cm未満) 、剣、やり及びなぎなたがあります。
○登録証の付いていない刀剣類は、譲り受け、譲り渡し(売り、買い、もらうことなど)はできません。もし登録証のない刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署へ「すみやかに」刀剣 類を発見した旨を連絡し、指示にしたがい警察署へ持参します。警察署は、刀剣類の発見を受理し、「発見届出清書」を交付し、各都道府県の教育委員会で実施している登録審査会の日時と場所を教えでくれます。
○登録審査は、その刀剣類が美術品としてまたは骨董品として登録できる条件を備えているかど うかを鑑定するものです。刀の形をしていても、古来の日本刀の製法で作られていなければ登録はできません。
○登録証の付いている刀剣=美術品と認定された刀剣類は、誰でも所持することができます。
○刀剣類を譲り受けた時は、届け出なければなりません。登録証を発行した都道府県の教育委員会あてに新しい所有者が、所有者変更届出書(県のHPで入手出来ます)を却日以内に提出します。「所有者変更届出書」をコピーして必要事項を記入し(印鑑不要)、送付するだけと手続きは簡単です。譲り渡した場合は、相手に届出をしてもらいましょう。
○所有者変更の届けをしていない場合は、銃刀法に違反している状態であり、登録証を紛失した時の再交付手続きも面倒になります。 例えば、下記のような場合に所有者変更届出善が必要です。
1)刀匠に注文した場合
新作刀の場合、新規登録時の所有者は制作者となっています
新作刀を購入した時、 所有者変更届けが必要です。
****************************************
刀匠に自分の好きな姿・刃文の日本刀製作を依頼することができます。新作刀展覧会(財団法人 日本美術刀剣保存協会主催)などで好みの作風、作者を見つけていただければ幸いです。 銃刀法上、刃渡60cm以上の刀は、15日以上、刃渡60cm未満のものは、10日以上かけて製作しなければなりません。製作日の重複は認められていませんつまり、年間に製作可能な本数には限界があり(2口)、日本文化を継承する観点から「大量に作って安価にする」 ことができないようになっています。それにより価格は、過去のコンクールの成績や自己評価、15日、10日 といった時間的数値、材料費、外注工賃などによって決まってきます。
*実際の製作期間は注文から納品まで6ヶ月程、武用の拵えをも含めるとさらに6ヶ月はかかりると思っていても良いと思います。(事務局)
新作刀の場合、新規登録時の所有者は制作者となっています
新作刀を購入した時、 所有者変更届けが必要です。
****************************************
刀匠に自分の好きな姿・刃文の日本刀製作を依頼することができます。新作刀展覧会(財団法人 日本美術刀剣保存協会主催)などで好みの作風、作者を見つけていただければ幸いです。 銃刀法上、刃渡60cm以上の刀は、15日以上、刃渡60cm未満のものは、10日以上かけて製作しなければなりません。製作日の重複は認められていませんつまり、年間に製作可能な本数には限界があり(2口)、日本文化を継承する観点から「大量に作って安価にする」 ことができないようになっています。それにより価格は、過去のコンクールの成績や自己評価、15日、10日 といった時間的数値、材料費、外注工賃などによって決まってきます。
*実際の製作期間は注文から納品まで6ヶ月程、武用の拵えをも含めるとさらに6ヶ月はかかりると思っていても良いと思います。(事務局)
2)新たに見つかったり、譲ってもらった場合 家の片付けをしていて出てきた、知人から譲ってもらった時など。(登録証付)
3)刀剣商・古物商などから購入した場合 好みや予算に応じて、平安時代から現代までの刀剣類を購入することができます。 過去に作られた刀剣類は、長年の研究によって作者に対する評価がなされていますが、 出来ばえや保存状態・伝来によって同じ作者でも価格が異なります。 刀の姿は、時代によって特色があるため作者銘がなくても作られた時代がほぼ特定 され、遠い過去の時代の息吹を身近に感じることができます。信頼のおけるところから購入しましょう。
明治9年の廃刀令によって、日本の伝統文化の象徴であった刀剣をめぐる世界は激変しました。それによって、長い伝統の中で培われてきた知識や技術のいくつかが失われていきましたが、今それを蘇らせようとしています。
刀剣は日本人の守護として、その精神性は生活に溶け込んでいました。刀身はもとより、その刀身を収める拵えに品格や美しさが求められ、それぞれの必要に応じたものが作られていました。
刀剣ブームと言われた昭和40年代に、それまで90年近くにわたって眠っていた多くの拵え入りの刀が、自鞘の刀として生き残りました。刀身美を観賞する白鞘の刀に加え、いにしえの日本文化を実感できる拵えの美も楽しんでいただきたいものであります。
明治9年の廃刀令によって、日本の伝統文化の象徴であった刀剣をめぐる世界は激変しました。それによって、長い伝統の中で培われてきた知識や技術のいくつかが失われていきましたが、今それを蘇らせようとしています。
刀剣は日本人の守護として、その精神性は生活に溶け込んでいました。刀身はもとより、その刀身を収める拵えに品格や美しさが求められ、それぞれの必要に応じたものが作られていました。
刀剣ブームと言われた昭和40年代に、それまで90年近くにわたって眠っていた多くの拵え入りの刀が、自鞘の刀として生き残りました。刀身美を観賞する白鞘の刀に加え、いにしえの日本文化を実感できる拵えの美も楽しんでいただきたいものであります。